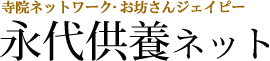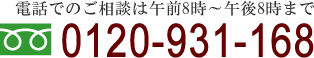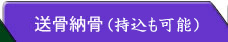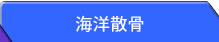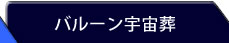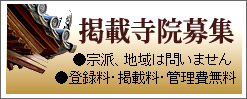|
当社サイト、カタログ等に記載されている「お坊さんjp」「永代供養ネット」「送骨納骨 」は当社の登録商標または商標です。 」は当社の登録商標または商標です。
なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。
|
|
|
永代供養の納骨先種類
|

永代供養のタイプ(納骨先)は色々ありますが、まずはお客様がどのようなご供養内容をご希望されるかです。
永代供養の金額、場所、交通の利便性、屋内型、屋外型、など永代に渡りのご供養ですので納骨先を慎重にお選びください。
棚型永代供養、ロッカー型永代供養、室内型墓石型永代供養、仏壇型永代供養、自動搬送式永代供養、位牌型永代供養、合祀型(合同墓)永代供養などがあり、近年は樹木葬(自然葬)、宇宙葬など色々あります。
永代供養のタイプの中でも半永久的に個別のご供養、お客様と契約期間内個別のご供養、ご供養の期間が7回忌、17回忌、33回忌個別のご供養で、その後、合祀墓(合葬墓、共同墓、合同墓)となる永代供養もありますので良く確認しお探しください。
【永代供養と永代使用料の違い】
永代供養とは契約期間中はご供養のすべてをお任せできる事で永代使用料とは土地などを使用する権利の事です。
一般的にはお墓を契約する際に所得するものです。
所得することにより、お墓を後継者に引き継げます。
 永代使用料はお墓の土地代の事です。 永代使用料はお墓の土地代の事です。
【永代供養の相場】
永代供養の相場は、ご利用いただきます永代供養の内容により大きく異なります。
一般的には10万円から100万円程度と言われております。
この金額の開きは下記のとおりです。
|
|
|